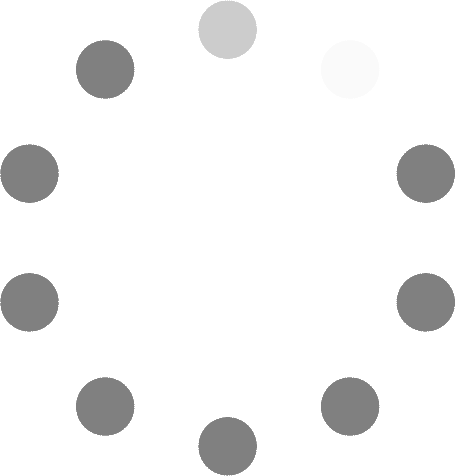俳句をタップ・クリックしてみて下さい。
寒雀羽根を膨らせ丸くなり
寒い朝に雀たちが、小さな身体で寒さに耐えています。全身の羽を膨らせ、丸っこく膨らんでいる様子が可愛らしいです。
木枯らしや家路を急ぐ人の群れ
冬の木枯らしが吹く中、少しでも早く暖かな我が家に帰宅しその寒さから逃れ、暖まろうと人々は家路を急ぎます。
堂々と生きて行けよと石蕗の花
石蕗は、寒い季節に寒さをものともせず、堂々と黄色い花を咲かせます。私も堂々と生きて行こうと思います。
仮名法語一冊持って冬籠り
仏者が「かな」まじりで誰にも分かるように仏教の大道を説いたものを「仮名法語」と言います。私も「仮名法語」を読みます。
手は縮め足は伸ばしてこたつかな
冬にこたつに入ると、あたかも足はこたつの中で伸ばし暖まり、こたつの外にある手は寒いので、縮めているようです。
雪降や犬もこたつで丸くなり
「猫はこたつで丸くなり」といいますが、我が家で飼っていた雑種の犬は、雪が積もると、こたつで丸くなっておりました。
侘助やポタリと落つる音を聴く
坐禅は習熟してくると、線香の灰が落ちる音が聴こえると言われますが、侘助が落ちる音も聴こえるようになりたいです。
冬木立夕暮れ時の凄さかな
夕暮れ時の冬木立には、何かしか、凄みを感じます。厳寒の中ひたすら寒さに耐える姿、忍耐力に、凄みを感じます。
落ち葉踏む音にためらう散歩道
冬の乾燥した落ち葉を踏むと踏み潰す音に、落ち葉が可哀そうに感じます。踏んで良いものか、踏むのを少し躊躇致します。
年の瀬や時計の針の早さかな
年の瀬と言う通り、時間の流れがとても早く感じるのは例年のことです。腕時計の針の回りもことのほか早く感じます。
白菜を洗いし水の冷たさや
白菜をはじめとした冬野菜を沢山入れた鍋料理で暖まるのが楽しみです。しかし、白菜を洗う水道水は実に冷たいのです。
傾いていく陽のなかの冬木立
昼間の冬木立とは違って、夕暮れ時の陽が傾いていく中の冬木立は、我慢・忍耐と言って良いでしょうか、凄みを感じます。
短日や一切衆生皆平等
冬の陽は短日ですが、一切の生きとし生ける生き物たちに、短日は与えられ平等で、そこに何か真理めいたものを感じます。
よくもまあ残り二日の年の暮れ
私の計画性のなさゆえに、年の暮れに残り二日のギリギリになって、年越しの準備に忙しくするのが例年の私の常であります。
年の暮時計の針も早くなり
年の暮れは、年の瀬や師走とも言われるように、時間の流れがことのほか早く感じられます。時計の針の動きも早いものです。
冬枯れや松の緑が目立ちける
臨済禅師が松の木を植えた話が『臨済録』に出てまいります。冬の松の木の緑はことのほか目立ち、映えるものであります。
寒風をものともせずに石蕗の花
石蕗は、冬に花を咲かせます。寒風をものともせず、黄色い明るい花を元気に咲かす石蕗に、なにがしか凄みを感じます。
木枯らしに背を向け歩く細き道
「細き道」とは、私の人生と捉えても良いかも知れません。冬の木枯らしに背を向け、寒さに耐えつつ一歩一歩をゆっくりと。
山茶花の周りほのかに暖かく
冬の寒い時期に、山茶花は明るい色の花を元気に咲かせます。花の周りのところだけ、少しばかり暖かさを感じる私です。
托鉢の僧が街行く年の暮
私の住む町には、臨済宗の僧堂がありまして、寒さ厳しき中、雲水さんが年末に托鉢をする姿を拝見することがあります。